1.はじめに
われわれの身の回りには多くの対立関係が存在する。冷戦時代の米ソ対立をはじめ、与党と野党の対立、政府と国民の対立、また友人との対立など、数えあげればきりがない。このような対立関係が存在するとき、さまざまな方法で解決への道が模索され、安定な秩序が形成されていく。戦争のように勝敗を決し、一方が他方を打ちのめして秩序を形成することもあれば、二者間の協調により、よりよい秩序が形成されていくこともある。ところがこのような二者間の対立ではなく、三者が対立関係にある事態も存在する。いわゆる、三角関係、三つどもえの戦いである。かつての米中ソの三極対立、日本・中国・台湾関係、男女間の三角関係などが思い浮ぶ。このような三角関係では、一方を立てれば他方が立たず、他方を立てれば一方が立たずと、二者対立とは異なる難しさが存在する。三角関係は二者対立の積み重ねではなく、二者間対立とは本質的に異なる問題点が存在する。一方、「三人寄れば文殊の知恵」と言われるように、数以上の名案が浮かぶこともあり、二と三とは大いに異なることは先人も気づいていた。
自然界でも多くの現象や相関関係は二体間の相互作用の積み重ねとして理解することができる。ところが自然界にも三角関係、三つどもえの争いが存在し、これらは二体間の相互作用の積み重ねだけでは理解できない。その例をお話ししよう。
2.自然界の三角関係
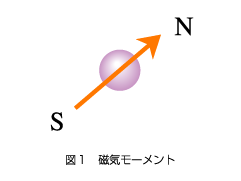 あらゆる物質は原子やイオンから構成されているが、原子やイオンの多くは、重さや電荷のような属性の他に、N極とS極を持った磁石の性質を持っている。この磁石は図1に示すようにS極からN極への方向に引いた矢印すなわちべクトルで表わされ、磁気モーメントと呼ばれている。この原子・イオンの微小磁石すなわち磁気モーメントがわれわれに身近な棒磁石、そして物質の磁気的性質の根元になっている。 あらゆる物質は原子やイオンから構成されているが、原子やイオンの多くは、重さや電荷のような属性の他に、N極とS極を持った磁石の性質を持っている。この磁石は図1に示すようにS極からN極への方向に引いた矢印すなわちべクトルで表わされ、磁気モーメントと呼ばれている。この原子・イオンの微小磁石すなわち磁気モーメントがわれわれに身近な棒磁石、そして物質の磁気的性質の根元になっている。
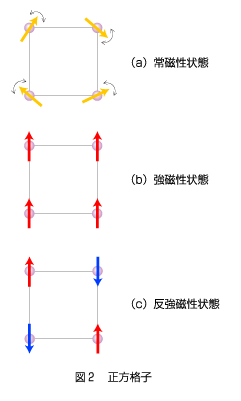 ところで、あらゆる物質は高温では気体であり、温度が下がると液体になり、さらに温度が下がると固体になる。このような状態の変化は相転移と呼ばれている。高温では原子や分子等の粒子は大きな熱的運動エネルギーをもち、乱雑に空間を動き回っている。これが気体状態である。ところが温度が下がり熱的運動が納まってくると、粒子間の相互作用が効きだし、粒子がくっつき合い、液体、そして固体という秩序状態に落ち着いていく。固体物質の磁気的性質についてもこれと同じような相転移現象が起こっている。この場合、変化するのは磁気モーメントの方向である。今、磁気モーメントを持った原子・イオンが図2に示すように正方形の関係で並んでいるとする。それぞれの原子・イオンが持っている磁気モーメントの向きは、温度が高いときには、図2(a) に示すように、熱エネルギーにより乱雑な方向を向き、時間的にも激しく方向を変えている。これは気体状態に当たり、常磁性状態と呼ばれている。ところが温度を下げると磁気モーメント間の相互作用が効きだし、磁気モーメントの向きが互いにそろった状態になる。この相互作用は二体間の相互作用であり、磁気モーメントを互いに平行にしようとする相互作用であると、図2(b) のように全部の磁気モーメントが一方向にそろった秩序状態になる。このような状態を強磁性状態といい、一般に磁石と呼ばれている永久磁石になる。ところが物質によっては磁気モーメントが互いに反対向きになるような相互作用を持つものもある。この場合には、図2(c) に示すように隣同士が互いに反対向きになった秩序状態が実現する。このような秩序状態は反強磁性状態と呼ばれている。 ところで、あらゆる物質は高温では気体であり、温度が下がると液体になり、さらに温度が下がると固体になる。このような状態の変化は相転移と呼ばれている。高温では原子や分子等の粒子は大きな熱的運動エネルギーをもち、乱雑に空間を動き回っている。これが気体状態である。ところが温度が下がり熱的運動が納まってくると、粒子間の相互作用が効きだし、粒子がくっつき合い、液体、そして固体という秩序状態に落ち着いていく。固体物質の磁気的性質についてもこれと同じような相転移現象が起こっている。この場合、変化するのは磁気モーメントの方向である。今、磁気モーメントを持った原子・イオンが図2に示すように正方形の関係で並んでいるとする。それぞれの原子・イオンが持っている磁気モーメントの向きは、温度が高いときには、図2(a) に示すように、熱エネルギーにより乱雑な方向を向き、時間的にも激しく方向を変えている。これは気体状態に当たり、常磁性状態と呼ばれている。ところが温度を下げると磁気モーメント間の相互作用が効きだし、磁気モーメントの向きが互いにそろった状態になる。この相互作用は二体間の相互作用であり、磁気モーメントを互いに平行にしようとする相互作用であると、図2(b) のように全部の磁気モーメントが一方向にそろった秩序状態になる。このような状態を強磁性状態といい、一般に磁石と呼ばれている永久磁石になる。ところが物質によっては磁気モーメントが互いに反対向きになるような相互作用を持つものもある。この場合には、図2(c) に示すように隣同士が互いに反対向きになった秩序状態が実現する。このような秩序状態は反強磁性状態と呼ばれている。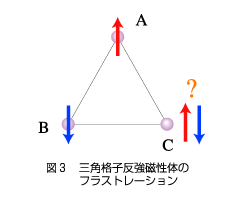
さて、このように磁気モーメントを反対向きにそろえる反強磁性相互作用を持った磁気モーメントが、図3に示すように三角形の関係に位置しているとどうなるだろうか。Aの磁気モーメントが上を向いているとするとBの磁気モーメントは下を向くことになる。ところがCのモーメントはBと反対向きということからは上を向こうとするが、Aとの関係では下を向かなければならず、結局、どちらを向けばいいか悩んでしまうことになる。このような現象は心理学用語を流用してフラストレーション効果と呼ばれている。自然界の物質は温度を下げると必ず秩序状態に落ち着き、エントロピーがゼロになることが知られているが、三角形の配置では相互作用そのものが競合し、秩序状態がとれない。このような三角関係を持った物質は現実に自然界に存在し、また合成することができる。このような物質でも秩序化は起こるのだろうか。起こるとすれば、どのようにして秩序化が起こり、その秩序状態はどのようなものなのだろうか。フラストレーション系反強磁性体はこのような二体問題にはない三体独特の問題を含む新たな系として注目を集めてきた。このような物質の例として三角格子反強磁性体やかごめ格子反強磁性体がある。
このような物質内部の微小な磁気モーメントの秩序形成過程や揺らぎはどのようにして観測することができるのだろうか。われわれはこのようなミクロな世界の情報を得る手段として核磁気共鳴(NMR)法を用いている。この実験手段について次に簡単に紹介しよう。
3.核磁気共鳴法
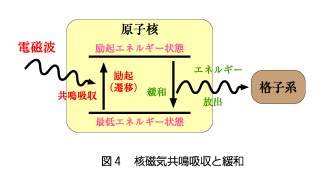 核磁気共鳴(NMR)法は原子のさらに内部の原子核を物質内部のミクロな情報の検出体として利用するものである。原子核も磁気モーメント(核磁気モーメント)を持った微小磁石である。この核磁気モーメントに磁場がかかっていると原子核は磁気エネルギーを持つが、このようなミクロな世界でのエネルギーは量子力学で説明されるように、連続量ではなくとびとびの量である。原子核は熱平衡状態ではその中の最も低いエネルギー状態にあり、次の高い励起エネルギー状態はある大きさだけ離れている。磁場中の原子核ではこのエネルギー間隔(ΔE)が磁場(H)の大きさに比例(ΔE=γhH/2π)している。ここでhはプランク定数であり、γは原子核毎に異なる固有の定数である。図4に示すように、このエネルギー間隔にちょうど一致したエネルギーを持つ電磁波を外部から入れてやると、原子核はこのエネルギーを吸収して最低エネルギー状態から上の励起エネルギー状態へ遷移する。この現象を核磁気共鳴という。電磁波のエネルギー(ε)は角周波数(ω)に比例(ε=hω/2π)しているので、結局、共鳴(∴ΔE=ε)を起こすことができる電磁波の角周波数は磁場に比例(ω=γH)することになる。外部からかけてやる電磁波の角周波数(ω)はわかっているので、共鳴が起こればこの関係式から原子核位置における内部磁場の強さ(H)を知ることができ、さらにその内部磁場を作り出している周りの原子・イオンの磁気モーメントについての情報を得ることができる。 核磁気共鳴(NMR)法は原子のさらに内部の原子核を物質内部のミクロな情報の検出体として利用するものである。原子核も磁気モーメント(核磁気モーメント)を持った微小磁石である。この核磁気モーメントに磁場がかかっていると原子核は磁気エネルギーを持つが、このようなミクロな世界でのエネルギーは量子力学で説明されるように、連続量ではなくとびとびの量である。原子核は熱平衡状態ではその中の最も低いエネルギー状態にあり、次の高い励起エネルギー状態はある大きさだけ離れている。磁場中の原子核ではこのエネルギー間隔(ΔE)が磁場(H)の大きさに比例(ΔE=γhH/2π)している。ここでhはプランク定数であり、γは原子核毎に異なる固有の定数である。図4に示すように、このエネルギー間隔にちょうど一致したエネルギーを持つ電磁波を外部から入れてやると、原子核はこのエネルギーを吸収して最低エネルギー状態から上の励起エネルギー状態へ遷移する。この現象を核磁気共鳴という。電磁波のエネルギー(ε)は角周波数(ω)に比例(ε=hω/2π)しているので、結局、共鳴(∴ΔE=ε)を起こすことができる電磁波の角周波数は磁場に比例(ω=γH)することになる。外部からかけてやる電磁波の角周波数(ω)はわかっているので、共鳴が起こればこの関係式から原子核位置における内部磁場の強さ(H)を知ることができ、さらにその内部磁場を作り出している周りの原子・イオンの磁気モーメントについての情報を得ることができる。
この核磁気共鳴を医療に応用したものが、最近、人体の断層写真を撮る診断法として知られているMRI(磁気共鳴イメージング)である。これは体内の60%を占める水の中の原子核である陽子に対して核磁気共鳴を起こさせるもので、人体に磁場をかけ、しかも場所によってわずかずつ磁場の大きさを変えてやる。ここである周波数の電磁波を照射すると、共鳴条件を満たす磁場がかかっている陽子だけが共鳴を起こすので、磁場の違いを位置の違いとして観測することができ、人体内の水の分布状態を知ることができる。すなわち水の分布図として体の断層写真が得られるのである。
さて話を一般論に戻そう。再び図4を見ていただこう。共鳴を起こして励起エネルギー状態に遷移させられた原子核は、電磁波が切られると、エネルギーを周りの格子系へ放出しながら最低エネルギー状態へ再び戻っていく。これを緩和という。戻っていく回復時間はスピン格子緩和時間と呼ばれ、この緩和時間から原子核の周りの原子・イオンの磁気モーメントの揺らぎ状態、動的な運動状態についての情報を得ることができる。
われわれは、このように物質内部のミクロな情報を得ることができる核磁気共鳴法を用いて、熱的錯乱が小さくなる極低温度域において、フラストレーションを持つ磁性体の秩序形成過程やその秩序状態について実験的研究を行っている。それらの研究成果について次にお話ししよう。
4.三角格子反強磁性体
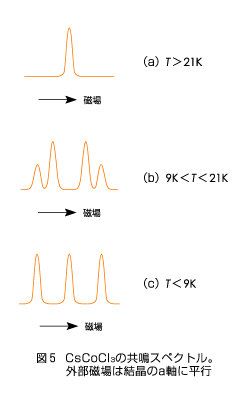 三角格子反強磁性体の例としてCsCoCl3という物質がある。このなかのコバルトイオンCo2+が磁気モーメントを持って三角格子を組んでおり、セシウム核133Csに対して核磁気共鳴を行う。ある周波数の電磁波をこの物質に照射し、外部磁場を掃引していくと共鳴が起こった磁場で信号が現れる。横軸に磁場、縦軸に信号強度を描いたグラフを共鳴スペクトルという。この物質の温度を変えていくと絶対温度21K(ケルビン)と9Kとで共鳴スペクトルが大きく変化することがわかった。図5に示すように、21Kより高温では1本のスペクトルピークのみが観測されるが、21Kと9Kの中間の温度域では4本のピークが観測され、さらに温度を下げて9K以下になると3本のピークに変化した。これらのスペクトルからこの物質は無秩序状態から温度を下げると、21Kと9Kで2回逐次的に相転移をし、1回目の相転移では三角格子上の3つの磁気モーメントの内2つは反平行に秩序化するが、1つは無秩序状態のままであり、2回目の相転移ですべての磁気モーメントが秩序化することがわかった。この秩序化には磁気モーメント間の小さな次近接相互作用が重要な役割を演じていることが理論的に明らかになっている。通常の磁性体では1回の相転移で無秩序状態から秩序状態へ一気に変化するが、このフラストレーション磁性体では逐次相転移をし、中間温度領域では部分的にのみ秩序化し、低温相ではじめてすべてが秩序化するのだ。さらにスピン格子緩和時間の測定から、中間域の部分秩序相ではソリトンと呼ばれる非線形な磁壁の移動伝播が存在することが明らかになった。 三角格子反強磁性体の例としてCsCoCl3という物質がある。このなかのコバルトイオンCo2+が磁気モーメントを持って三角格子を組んでおり、セシウム核133Csに対して核磁気共鳴を行う。ある周波数の電磁波をこの物質に照射し、外部磁場を掃引していくと共鳴が起こった磁場で信号が現れる。横軸に磁場、縦軸に信号強度を描いたグラフを共鳴スペクトルという。この物質の温度を変えていくと絶対温度21K(ケルビン)と9Kとで共鳴スペクトルが大きく変化することがわかった。図5に示すように、21Kより高温では1本のスペクトルピークのみが観測されるが、21Kと9Kの中間の温度域では4本のピークが観測され、さらに温度を下げて9K以下になると3本のピークに変化した。これらのスペクトルからこの物質は無秩序状態から温度を下げると、21Kと9Kで2回逐次的に相転移をし、1回目の相転移では三角格子上の3つの磁気モーメントの内2つは反平行に秩序化するが、1つは無秩序状態のままであり、2回目の相転移ですべての磁気モーメントが秩序化することがわかった。この秩序化には磁気モーメント間の小さな次近接相互作用が重要な役割を演じていることが理論的に明らかになっている。通常の磁性体では1回の相転移で無秩序状態から秩序状態へ一気に変化するが、このフラストレーション磁性体では逐次相転移をし、中間温度領域では部分的にのみ秩序化し、低温相ではじめてすべてが秩序化するのだ。さらにスピン格子緩和時間の測定から、中間域の部分秩序相ではソリトンと呼ばれる非線形な磁壁の移動伝播が存在することが明らかになった。
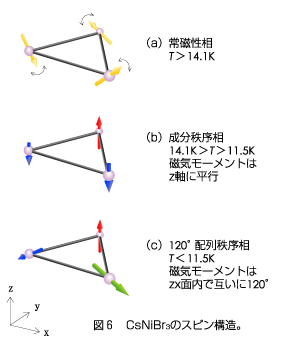 さて、この物質では磁気モーメントが上向きか下向きかのいずれかしか選択できない性質を持っている。この相互作用はイジング型と呼ばれている。一方、xyzで表される三次元空間の任意の方向に磁気モーメントが向きうる物質も存在する。このような相互作用はハイゼンベルク型と呼ばれている。このような系でフラストレーションがあるとどのような相転移と秩序相がみられるであろうか。CsNiBr3という物質はこの例に当たり、Ni2+イオンが三角格子を形成している。セシウム核133Csの核磁気共鳴実験から14.1Kと11.5Kで2回相転移が起こっていることが分かった。この物質においては、11.5K以下の低温相においては図6(c) に示すように3つの磁気モーメントが互いに120°の角度をなして秩序状態を形成する。本来は互いに反対向きになりたいのだが、それができず、互いに120°で辛抱し丸く納まっているのである。2つの転移点14.1Kと11.5Kの間の中間相では結晶内にわずかでも向きやすい異方性があるとそちらの方向の成分のみが先に秩序化する。CsNiBr3ではz軸方向にわずかに異方性があり、中間相では図6(b) に示すようにz軸への射影成分のみが秩序化し、各磁気モーメントは+1、−1/2、−1/2の大きさを持つ。この中間相は磁気モーメントのxyz成分の内、z成分のみが秩序化し、他のx、y成分は無秩序のままであることから成分秩序相と呼ばれている。 さて、この物質では磁気モーメントが上向きか下向きかのいずれかしか選択できない性質を持っている。この相互作用はイジング型と呼ばれている。一方、xyzで表される三次元空間の任意の方向に磁気モーメントが向きうる物質も存在する。このような相互作用はハイゼンベルク型と呼ばれている。このような系でフラストレーションがあるとどのような相転移と秩序相がみられるであろうか。CsNiBr3という物質はこの例に当たり、Ni2+イオンが三角格子を形成している。セシウム核133Csの核磁気共鳴実験から14.1Kと11.5Kで2回相転移が起こっていることが分かった。この物質においては、11.5K以下の低温相においては図6(c) に示すように3つの磁気モーメントが互いに120°の角度をなして秩序状態を形成する。本来は互いに反対向きになりたいのだが、それができず、互いに120°で辛抱し丸く納まっているのである。2つの転移点14.1Kと11.5Kの間の中間相では結晶内にわずかでも向きやすい異方性があるとそちらの方向の成分のみが先に秩序化する。CsNiBr3ではz軸方向にわずかに異方性があり、中間相では図6(b) に示すようにz軸への射影成分のみが秩序化し、各磁気モーメントは+1、−1/2、−1/2の大きさを持つ。この中間相は磁気モーメントのxyz成分の内、z成分のみが秩序化し、他のx、y成分は無秩序のままであることから成分秩序相と呼ばれている。
これら2つの例からわかるように、フラストレーション系磁性体においては格子の空間次元や相互作用の対称性によって変化に富んだ相転移現象が起こる。
5.かごめ格子反強磁性体
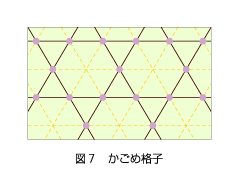 三角格子から1つおきに格子点を除いていくと、図7に示すように六角形と三角形が組み合わさったかごめ格子になる。これは図8に示したような、昔日本で広く使われていた、竹で編んだ篭目の模様である。三角格子では隣り合う三角形が互いに辺を共有しているが、かごめ格子では隣り合う三角形は1点を共有するのみであり、三角形間の相関が小さくなる。かごめ格子点上に反強磁性相互作用をする磁気モーメントが存在する磁性体をかごめ格子反強磁性体と言い、実際、このような物質が存在する。磁気モーメント間の相互作用がハイゼンベルク型相互作用であると、最低エネルギー状態においては単位三角格子上のモーメントは互いに120°ずつずれた方向を向くが、かごめ格子全体ではモーメントの配列方法は無数に存在する。その内の3つの配列の例を図9に示した。このように最低エネルギー状態が無数に存在することは、絶対零度においても秩序状態にならず、また熱力学第二法則に反してエントロピーがゼロでないことを意味する。このようなかごめ格子反強磁性体では極低温度において今までに知られていない新しい秩序状態や未知の現象が出現する可能性がある。理論的に、隣り合う2つのモーメントがペアーになって物質内を動き回るという、超流動や超伝導に対応するような状態が出現するという予想もある。 三角格子から1つおきに格子点を除いていくと、図7に示すように六角形と三角形が組み合わさったかごめ格子になる。これは図8に示したような、昔日本で広く使われていた、竹で編んだ篭目の模様である。三角格子では隣り合う三角形が互いに辺を共有しているが、かごめ格子では隣り合う三角形は1点を共有するのみであり、三角形間の相関が小さくなる。かごめ格子点上に反強磁性相互作用をする磁気モーメントが存在する磁性体をかごめ格子反強磁性体と言い、実際、このような物質が存在する。磁気モーメント間の相互作用がハイゼンベルク型相互作用であると、最低エネルギー状態においては単位三角格子上のモーメントは互いに120°ずつずれた方向を向くが、かごめ格子全体ではモーメントの配列方法は無数に存在する。その内の3つの配列の例を図9に示した。このように最低エネルギー状態が無数に存在することは、絶対零度においても秩序状態にならず、また熱力学第二法則に反してエントロピーがゼロでないことを意味する。このようなかごめ格子反強磁性体では極低温度において今までに知られていない新しい秩序状態や未知の現象が出現する可能性がある。理論的に、隣り合う2つのモーメントがペアーになって物質内を動き回るという、超流動や超伝導に対応するような状態が出現するという予想もある。 われわれはかごめ格子反強磁性体の例として、ジャロサイトと呼ばれる一群の物質RM3 (OH) 6 (SO4) 2を対象として、極低温度において超伝導量子干渉磁束計(SQUID)や核磁気共鳴法を用いてその磁気的性質を調べている。右の分子式でRはK(カリウム)やNa(ナトリウム)、Rb(ルビジュウム)等の原子であり、MはFe(鉄)またはCr(クロム)原子である。その実験から鉄ジャロサイト系は温度65K、クロムジャロサイト系は温度4Kで磁気相転移をすることが明らかになった。これらの磁気相転移温度はモーメント間の相互作用に比べて非常に低温であり、フラストレーション効果のために相転移が非常に起こりにくくなっていることを示している。 われわれはかごめ格子反強磁性体の例として、ジャロサイトと呼ばれる一群の物質RM3 (OH) 6 (SO4) 2を対象として、極低温度において超伝導量子干渉磁束計(SQUID)や核磁気共鳴法を用いてその磁気的性質を調べている。右の分子式でRはK(カリウム)やNa(ナトリウム)、Rb(ルビジュウム)等の原子であり、MはFe(鉄)またはCr(クロム)原子である。その実験から鉄ジャロサイト系は温度65K、クロムジャロサイト系は温度4Kで磁気相転移をすることが明らかになった。これらの磁気相転移温度はモーメント間の相互作用に比べて非常に低温であり、フラストレーション効果のために相転移が非常に起こりにくくなっていることを示している。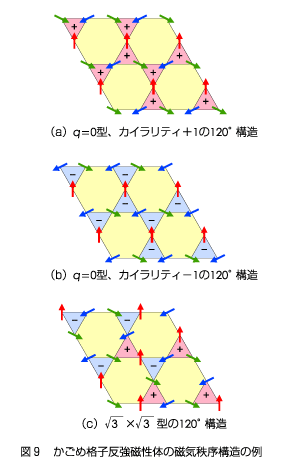 秩序相における磁気構造は図9(a) のような構造であることが明らかになった。図9の3つの秩序配列においてはカイラリティという物理量が重要な意味を持っている。カイラリティとは、1つの三角形を1周回るとき磁気モーメントも120°ずつ同じ方向に回転していれば+1であり、逆方向に回転していれば−1になると定義された物理量である。図9の各三角形の中心に記入した+、−がその三角形におけるカイラリティであり、(a)の構造では+ばかり、(b)の構造では−ばかり、(c)の構造では+と−が交互に並んでいる。これら3つの磁気配列はすべてエネルギーが等しく、同じ確率で実現するはずなのに、現実の物質では(a)の配列になっている。詳しい実験と解析から、この物質では、モーメント間相互作用の100分の1程度の非常に小さい異方性のために相転移が起こり、この秩序構造が選択されることが明らかになった。 秩序相における磁気構造は図9(a) のような構造であることが明らかになった。図9の3つの秩序配列においてはカイラリティという物理量が重要な意味を持っている。カイラリティとは、1つの三角形を1周回るとき磁気モーメントも120°ずつ同じ方向に回転していれば+1であり、逆方向に回転していれば−1になると定義された物理量である。図9の各三角形の中心に記入した+、−がその三角形におけるカイラリティであり、(a)の構造では+ばかり、(b)の構造では−ばかり、(c)の構造では+と−が交互に並んでいる。これら3つの磁気配列はすべてエネルギーが等しく、同じ確率で実現するはずなのに、現実の物質では(a)の配列になっている。詳しい実験と解析から、この物質では、モーメント間相互作用の100分の1程度の非常に小さい異方性のために相転移が起こり、この秩序構造が選択されることが明らかになった。
6.おわりに
本来なら温度が下がって熱エネルギーが減少すると、相互作用による協力現象で相転移をするはずなのに、相互作用そのものが競合しているためにフラストレーションが起こり、相転移が起こりにくく、逐次相転移をしたり、特異な磁気配列を形成したりする例をお話しした。これは100億分の1メートルという非常にミクロな原子の世界で起こっている現象であり、そのような世界の様子をわれわれは核磁気共鳴法という方法でのぞいてきた。このようなミクロな世界で起こっているフラストレ−ション現象は、最初に述べた人間や社会における三角関係ととてもよく似ているように思われる。相互作用が競合していると秩序化が起こりにくく、部分秩序化や成分秩序化に当たる秩序形成過程がわれわれの身の回りに見られる気がする。また、秩序化にあたって次近接相互作用や異方性に当る非常に小さい相互作用や力が全体の秩序化の大きな原動力になっていることが多々ある。ベルリンの壁の崩壊、ソ連の解体、明治維新、諸々の革命。歴史は緩やかに変化するよりも、単純な相互作用の積み重ねとしての協力現象によって相転移的に突然変化してきた。人民と権力との闘争による革命も自由と権力と命の三角関係の拮抗という見方をすれば、多くの動きが理解できるのではなかろうか。ミクロな世界の現象を研究してきたが、100億倍も大きな人間世界にも同じような現象が起こっているように見え、ミクロな世界の現象が複雑そうな人間環境解明のモデルになるかもしれないという思いがしてならない。
|

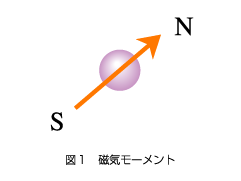 あらゆる物質は原子やイオンから構成されているが、原子やイオンの多くは、重さや電荷のような属性の他に、N極とS極を持った磁石の性質を持っている。この磁石は図1に示すようにS極からN極への方向に引いた矢印すなわちべクトルで表わされ、磁気モーメントと呼ばれている。この原子・イオンの微小磁石すなわち磁気モーメントがわれわれに身近な棒磁石、そして物質の磁気的性質の根元になっている。
あらゆる物質は原子やイオンから構成されているが、原子やイオンの多くは、重さや電荷のような属性の他に、N極とS極を持った磁石の性質を持っている。この磁石は図1に示すようにS極からN極への方向に引いた矢印すなわちべクトルで表わされ、磁気モーメントと呼ばれている。この原子・イオンの微小磁石すなわち磁気モーメントがわれわれに身近な棒磁石、そして物質の磁気的性質の根元になっている。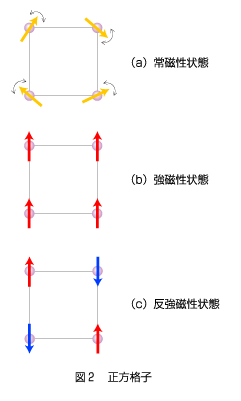 ところで、あらゆる物質は高温では気体であり、温度が下がると液体になり、さらに温度が下がると固体になる。このような状態の変化は相転移と呼ばれている。高温では原子や分子等の粒子は大きな熱的運動エネルギーをもち、乱雑に空間を動き回っている。これが気体状態である。ところが温度が下がり熱的運動が納まってくると、粒子間の相互作用が効きだし、粒子がくっつき合い、液体、そして固体という秩序状態に落ち着いていく。固体物質の磁気的性質についてもこれと同じような相転移現象が起こっている。この場合、変化するのは磁気モーメントの方向である。今、磁気モーメントを持った原子・イオンが図2に示すように正方形の関係で並んでいるとする。それぞれの原子・イオンが持っている磁気モーメントの向きは、温度が高いときには、図2(a) に示すように、熱エネルギーにより乱雑な方向を向き、時間的にも激しく方向を変えている。これは気体状態に当たり、常磁性状態と呼ばれている。ところが温度を下げると磁気モーメント間の相互作用が効きだし、磁気モーメントの向きが互いにそろった状態になる。この相互作用は二体間の相互作用であり、磁気モーメントを互いに平行にしようとする相互作用であると、図2(b) のように全部の磁気モーメントが一方向にそろった秩序状態になる。このような状態を強磁性状態といい、一般に磁石と呼ばれている永久磁石になる。ところが物質によっては磁気モーメントが互いに反対向きになるような相互作用を持つものもある。この場合には、図2(c) に示すように隣同士が互いに反対向きになった秩序状態が実現する。このような秩序状態は反強磁性状態と呼ばれている。
ところで、あらゆる物質は高温では気体であり、温度が下がると液体になり、さらに温度が下がると固体になる。このような状態の変化は相転移と呼ばれている。高温では原子や分子等の粒子は大きな熱的運動エネルギーをもち、乱雑に空間を動き回っている。これが気体状態である。ところが温度が下がり熱的運動が納まってくると、粒子間の相互作用が効きだし、粒子がくっつき合い、液体、そして固体という秩序状態に落ち着いていく。固体物質の磁気的性質についてもこれと同じような相転移現象が起こっている。この場合、変化するのは磁気モーメントの方向である。今、磁気モーメントを持った原子・イオンが図2に示すように正方形の関係で並んでいるとする。それぞれの原子・イオンが持っている磁気モーメントの向きは、温度が高いときには、図2(a) に示すように、熱エネルギーにより乱雑な方向を向き、時間的にも激しく方向を変えている。これは気体状態に当たり、常磁性状態と呼ばれている。ところが温度を下げると磁気モーメント間の相互作用が効きだし、磁気モーメントの向きが互いにそろった状態になる。この相互作用は二体間の相互作用であり、磁気モーメントを互いに平行にしようとする相互作用であると、図2(b) のように全部の磁気モーメントが一方向にそろった秩序状態になる。このような状態を強磁性状態といい、一般に磁石と呼ばれている永久磁石になる。ところが物質によっては磁気モーメントが互いに反対向きになるような相互作用を持つものもある。この場合には、図2(c) に示すように隣同士が互いに反対向きになった秩序状態が実現する。このような秩序状態は反強磁性状態と呼ばれている。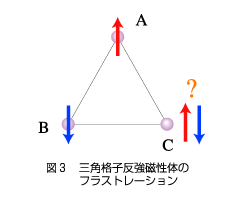
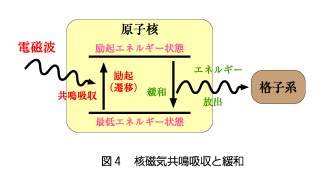 核磁気共鳴(NMR)法は原子のさらに内部の原子核を物質内部のミクロな情報の検出体として利用するものである。原子核も磁気モーメント(核磁気モーメント)を持った微小磁石である。この核磁気モーメントに磁場がかかっていると原子核は磁気エネルギーを持つが、このようなミクロな世界でのエネルギーは量子力学で説明されるように、連続量ではなくとびとびの量である。原子核は熱平衡状態ではその中の最も低いエネルギー状態にあり、次の高い励起エネルギー状態はある大きさだけ離れている。磁場中の原子核ではこのエネルギー間隔(ΔE)が磁場(H)の大きさに比例(ΔE=γhH/2π)している。ここでhはプランク定数であり、γは原子核毎に異なる固有の定数である。図4に示すように、このエネルギー間隔にちょうど一致したエネルギーを持つ電磁波を外部から入れてやると、原子核はこのエネルギーを吸収して最低エネルギー状態から上の励起エネルギー状態へ遷移する。この現象を核磁気共鳴という。電磁波のエネルギー(ε)は角周波数(ω)に比例(ε=hω/2π)しているので、結局、共鳴(∴ΔE=ε)を起こすことができる電磁波の角周波数は磁場に比例(ω=γH)することになる。外部からかけてやる電磁波の角周波数(ω)はわかっているので、共鳴が起こればこの関係式から原子核位置における内部磁場の強さ(H)を知ることができ、さらにその内部磁場を作り出している周りの原子・イオンの磁気モーメントについての情報を得ることができる。
核磁気共鳴(NMR)法は原子のさらに内部の原子核を物質内部のミクロな情報の検出体として利用するものである。原子核も磁気モーメント(核磁気モーメント)を持った微小磁石である。この核磁気モーメントに磁場がかかっていると原子核は磁気エネルギーを持つが、このようなミクロな世界でのエネルギーは量子力学で説明されるように、連続量ではなくとびとびの量である。原子核は熱平衡状態ではその中の最も低いエネルギー状態にあり、次の高い励起エネルギー状態はある大きさだけ離れている。磁場中の原子核ではこのエネルギー間隔(ΔE)が磁場(H)の大きさに比例(ΔE=γhH/2π)している。ここでhはプランク定数であり、γは原子核毎に異なる固有の定数である。図4に示すように、このエネルギー間隔にちょうど一致したエネルギーを持つ電磁波を外部から入れてやると、原子核はこのエネルギーを吸収して最低エネルギー状態から上の励起エネルギー状態へ遷移する。この現象を核磁気共鳴という。電磁波のエネルギー(ε)は角周波数(ω)に比例(ε=hω/2π)しているので、結局、共鳴(∴ΔE=ε)を起こすことができる電磁波の角周波数は磁場に比例(ω=γH)することになる。外部からかけてやる電磁波の角周波数(ω)はわかっているので、共鳴が起こればこの関係式から原子核位置における内部磁場の強さ(H)を知ることができ、さらにその内部磁場を作り出している周りの原子・イオンの磁気モーメントについての情報を得ることができる。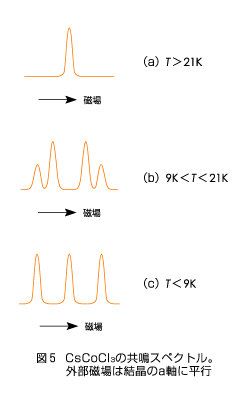 三角格子反強磁性体の例としてCsCoCl3という物質がある。このなかのコバルトイオンCo2+が磁気モーメントを持って三角格子を組んでおり、セシウム核133Csに対して核磁気共鳴を行う。ある周波数の電磁波をこの物質に照射し、外部磁場を掃引していくと共鳴が起こった磁場で信号が現れる。横軸に磁場、縦軸に信号強度を描いたグラフを共鳴スペクトルという。この物質の温度を変えていくと絶対温度21K(ケルビン)と9Kとで共鳴スペクトルが大きく変化することがわかった。図5に示すように、21Kより高温では1本のスペクトルピークのみが観測されるが、21Kと9Kの中間の温度域では4本のピークが観測され、さらに温度を下げて9K以下になると3本のピークに変化した。これらのスペクトルからこの物質は無秩序状態から温度を下げると、21Kと9Kで2回逐次的に相転移をし、1回目の相転移では三角格子上の3つの磁気モーメントの内2つは反平行に秩序化するが、1つは無秩序状態のままであり、2回目の相転移ですべての磁気モーメントが秩序化することがわかった。この秩序化には磁気モーメント間の小さな次近接相互作用が重要な役割を演じていることが理論的に明らかになっている。通常の磁性体では1回の相転移で無秩序状態から秩序状態へ一気に変化するが、このフラストレーション磁性体では逐次相転移をし、中間温度領域では部分的にのみ秩序化し、低温相ではじめてすべてが秩序化するのだ。さらにスピン格子緩和時間の測定から、中間域の部分秩序相ではソリトンと呼ばれる非線形な磁壁の移動伝播が存在することが明らかになった。
三角格子反強磁性体の例としてCsCoCl3という物質がある。このなかのコバルトイオンCo2+が磁気モーメントを持って三角格子を組んでおり、セシウム核133Csに対して核磁気共鳴を行う。ある周波数の電磁波をこの物質に照射し、外部磁場を掃引していくと共鳴が起こった磁場で信号が現れる。横軸に磁場、縦軸に信号強度を描いたグラフを共鳴スペクトルという。この物質の温度を変えていくと絶対温度21K(ケルビン)と9Kとで共鳴スペクトルが大きく変化することがわかった。図5に示すように、21Kより高温では1本のスペクトルピークのみが観測されるが、21Kと9Kの中間の温度域では4本のピークが観測され、さらに温度を下げて9K以下になると3本のピークに変化した。これらのスペクトルからこの物質は無秩序状態から温度を下げると、21Kと9Kで2回逐次的に相転移をし、1回目の相転移では三角格子上の3つの磁気モーメントの内2つは反平行に秩序化するが、1つは無秩序状態のままであり、2回目の相転移ですべての磁気モーメントが秩序化することがわかった。この秩序化には磁気モーメント間の小さな次近接相互作用が重要な役割を演じていることが理論的に明らかになっている。通常の磁性体では1回の相転移で無秩序状態から秩序状態へ一気に変化するが、このフラストレーション磁性体では逐次相転移をし、中間温度領域では部分的にのみ秩序化し、低温相ではじめてすべてが秩序化するのだ。さらにスピン格子緩和時間の測定から、中間域の部分秩序相ではソリトンと呼ばれる非線形な磁壁の移動伝播が存在することが明らかになった。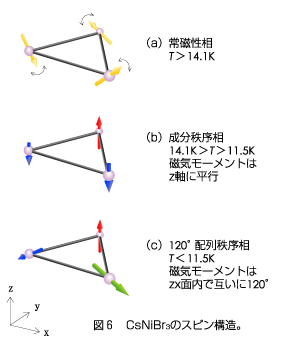 さて、この物質では磁気モーメントが上向きか下向きかのいずれかしか選択できない性質を持っている。この相互作用はイジング型と呼ばれている。一方、xyzで表される三次元空間の任意の方向に磁気モーメントが向きうる物質も存在する。このような相互作用はハイゼンベルク型と呼ばれている。このような系でフラストレーションがあるとどのような相転移と秩序相がみられるであろうか。CsNiBr3という物質はこの例に当たり、Ni2+イオンが三角格子を形成している。セシウム核133Csの核磁気共鳴実験から14.1Kと11.5Kで2回相転移が起こっていることが分かった。この物質においては、11.5K以下の低温相においては図6(c) に示すように3つの磁気モーメントが互いに120°の角度をなして秩序状態を形成する。本来は互いに反対向きになりたいのだが、それができず、互いに120°で辛抱し丸く納まっているのである。2つの転移点14.1Kと11.5Kの間の中間相では結晶内にわずかでも向きやすい異方性があるとそちらの方向の成分のみが先に秩序化する。CsNiBr3ではz軸方向にわずかに異方性があり、中間相では図6(b) に示すようにz軸への射影成分のみが秩序化し、各磁気モーメントは+1、−1/2、−1/2の大きさを持つ。この中間相は磁気モーメントのxyz成分の内、z成分のみが秩序化し、他のx、y成分は無秩序のままであることから成分秩序相と呼ばれている。
さて、この物質では磁気モーメントが上向きか下向きかのいずれかしか選択できない性質を持っている。この相互作用はイジング型と呼ばれている。一方、xyzで表される三次元空間の任意の方向に磁気モーメントが向きうる物質も存在する。このような相互作用はハイゼンベルク型と呼ばれている。このような系でフラストレーションがあるとどのような相転移と秩序相がみられるであろうか。CsNiBr3という物質はこの例に当たり、Ni2+イオンが三角格子を形成している。セシウム核133Csの核磁気共鳴実験から14.1Kと11.5Kで2回相転移が起こっていることが分かった。この物質においては、11.5K以下の低温相においては図6(c) に示すように3つの磁気モーメントが互いに120°の角度をなして秩序状態を形成する。本来は互いに反対向きになりたいのだが、それができず、互いに120°で辛抱し丸く納まっているのである。2つの転移点14.1Kと11.5Kの間の中間相では結晶内にわずかでも向きやすい異方性があるとそちらの方向の成分のみが先に秩序化する。CsNiBr3ではz軸方向にわずかに異方性があり、中間相では図6(b) に示すようにz軸への射影成分のみが秩序化し、各磁気モーメントは+1、−1/2、−1/2の大きさを持つ。この中間相は磁気モーメントのxyz成分の内、z成分のみが秩序化し、他のx、y成分は無秩序のままであることから成分秩序相と呼ばれている。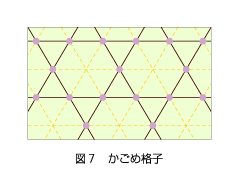 三角格子から1つおきに格子点を除いていくと、図7に示すように六角形と三角形が組み合わさったかごめ格子になる。これは図8に示したような、昔日本で広く使われていた、竹で編んだ篭目の模様である。三角格子では隣り合う三角形が互いに辺を共有しているが、かごめ格子では隣り合う三角形は1点を共有するのみであり、三角形間の相関が小さくなる。かごめ格子点上に反強磁性相互作用をする磁気モーメントが存在する磁性体をかごめ格子反強磁性体と言い、実際、このような物質が存在する。磁気モーメント間の相互作用がハイゼンベルク型相互作用であると、最低エネルギー状態においては単位三角格子上のモーメントは互いに120°ずつずれた方向を向くが、かごめ格子全体ではモーメントの配列方法は無数に存在する。その内の3つの配列の例を図9に示した。このように最低エネルギー状態が無数に存在することは、絶対零度においても秩序状態にならず、また熱力学第二法則に反してエントロピーがゼロでないことを意味する。このようなかごめ格子反強磁性体では極低温度において今までに知られていない新しい秩序状態や未知の現象が出現する可能性がある。理論的に、隣り合う2つのモーメントがペアーになって物質内を動き回るという、超流動や超伝導に対応するような状態が出現するという予想もある。
三角格子から1つおきに格子点を除いていくと、図7に示すように六角形と三角形が組み合わさったかごめ格子になる。これは図8に示したような、昔日本で広く使われていた、竹で編んだ篭目の模様である。三角格子では隣り合う三角形が互いに辺を共有しているが、かごめ格子では隣り合う三角形は1点を共有するのみであり、三角形間の相関が小さくなる。かごめ格子点上に反強磁性相互作用をする磁気モーメントが存在する磁性体をかごめ格子反強磁性体と言い、実際、このような物質が存在する。磁気モーメント間の相互作用がハイゼンベルク型相互作用であると、最低エネルギー状態においては単位三角格子上のモーメントは互いに120°ずつずれた方向を向くが、かごめ格子全体ではモーメントの配列方法は無数に存在する。その内の3つの配列の例を図9に示した。このように最低エネルギー状態が無数に存在することは、絶対零度においても秩序状態にならず、また熱力学第二法則に反してエントロピーがゼロでないことを意味する。このようなかごめ格子反強磁性体では極低温度において今までに知られていない新しい秩序状態や未知の現象が出現する可能性がある。理論的に、隣り合う2つのモーメントがペアーになって物質内を動き回るという、超流動や超伝導に対応するような状態が出現するという予想もある。 われわれはかごめ格子反強磁性体の例として、ジャロサイトと呼ばれる一群の物質RM3 (OH) 6 (SO4) 2を対象として、極低温度において超伝導量子干渉磁束計(SQUID)や核磁気共鳴法を用いてその磁気的性質を調べている。右の分子式でRはK(カリウム)やNa(ナトリウム)、Rb(ルビジュウム)等の原子であり、MはFe(鉄)またはCr(クロム)原子である。その実験から鉄ジャロサイト系は温度65K、クロムジャロサイト系は温度4Kで磁気相転移をすることが明らかになった。これらの磁気相転移温度はモーメント間の相互作用に比べて非常に低温であり、フラストレーション効果のために相転移が非常に起こりにくくなっていることを示している。
われわれはかごめ格子反強磁性体の例として、ジャロサイトと呼ばれる一群の物質RM3 (OH) 6 (SO4) 2を対象として、極低温度において超伝導量子干渉磁束計(SQUID)や核磁気共鳴法を用いてその磁気的性質を調べている。右の分子式でRはK(カリウム)やNa(ナトリウム)、Rb(ルビジュウム)等の原子であり、MはFe(鉄)またはCr(クロム)原子である。その実験から鉄ジャロサイト系は温度65K、クロムジャロサイト系は温度4Kで磁気相転移をすることが明らかになった。これらの磁気相転移温度はモーメント間の相互作用に比べて非常に低温であり、フラストレーション効果のために相転移が非常に起こりにくくなっていることを示している。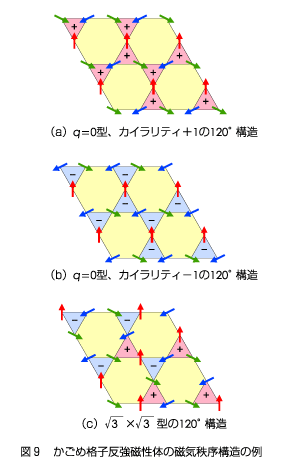 秩序相における磁気構造は図9(a) のような構造であることが明らかになった。図9の3つの秩序配列においてはカイラリティという物理量が重要な意味を持っている。カイラリティとは、1つの三角形を1周回るとき磁気モーメントも120°ずつ同じ方向に回転していれば+1であり、逆方向に回転していれば−1になると定義された物理量である。図9の各三角形の中心に記入した+、−がその三角形におけるカイラリティであり、(a)の構造では+ばかり、(b)の構造では−ばかり、(c)の構造では+と−が交互に並んでいる。これら3つの磁気配列はすべてエネルギーが等しく、同じ確率で実現するはずなのに、現実の物質では(a)の配列になっている。詳しい実験と解析から、この物質では、モーメント間相互作用の100分の1程度の非常に小さい異方性のために相転移が起こり、この秩序構造が選択されることが明らかになった。
秩序相における磁気構造は図9(a) のような構造であることが明らかになった。図9の3つの秩序配列においてはカイラリティという物理量が重要な意味を持っている。カイラリティとは、1つの三角形を1周回るとき磁気モーメントも120°ずつ同じ方向に回転していれば+1であり、逆方向に回転していれば−1になると定義された物理量である。図9の各三角形の中心に記入した+、−がその三角形におけるカイラリティであり、(a)の構造では+ばかり、(b)の構造では−ばかり、(c)の構造では+と−が交互に並んでいる。これら3つの磁気配列はすべてエネルギーが等しく、同じ確率で実現するはずなのに、現実の物質では(a)の配列になっている。詳しい実験と解析から、この物質では、モーメント間相互作用の100分の1程度の非常に小さい異方性のために相転移が起こり、この秩序構造が選択されることが明らかになった。